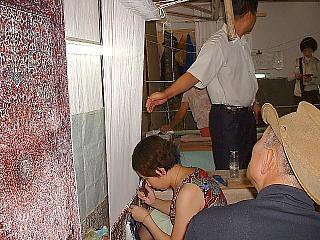敦煌(2004.7.28~8.4)
1.敦煌
7月30日(金)、朝7時30分発の飛行機で西安を飛び立って敦煌に行く。
約2時間一寸のフライトだ。飛行機から地上が良く見え、黄土の大地が続いている。これらが河西回廊か。西安から始まるシルクロードの幹線は3ルートあるが、みなここを通って新疆に入ってから分かれる。
回廊は南は祁連山脈、北も竜首山の山脈等に囲まれた長さ約1000km、幅約40~100kmの地域である。
シルクロードの歴史に重要な地位を占めている、古代の涼州(武威)、甘州(張掖)、粛州(酒泉)、沙州(敦煌)である。
これらの回廊はゴビ、砂漠、雪山、氷河が大部分。そして先程の4大オアシス。オアシスを離れると、そこはゴビと砂漠で、石と砂の世界だ。ゴビとは小石混じりの砂礫のことだ。
敦煌に近づくに連れ、頂に万年雪を持った祁連山脈が見える。時々眼下に見えるオアシスの諸都市は、あの祁連山脈の雪解け水を頼りに
暮らしているのだろう。
今回この原稿を記す前に、かって親しんだ井上靖の「敦煌」・「楼蘭」・「崑崙の玉」を読み直した。
これらの小説の舞台は今私が飛んでいる眼下にある。小説で読んだ地名が身近に感じられる。
敦煌とは盛大という意味らしい。古代、ここには遊牧民族の大月氏がいたが、のちに匈奴が占領した。漢の武帝が匈奴を追い払い、以後漢族が移住し、敦煌郡が置かれた。

10時前に敦煌空港に着いた。バスでまず本日の宿「敦煌太陽大酒店」に入る。

午後の観光は12時出発だ。風呂に浸かり休憩する。

集合前に少しだけ街をぶらぶらする。ホテルの直ぐそばに敦煌のシンボルである「反弾琵琶の大理石像」があった。莫高窟の壁画にある舞劇「シルクロードの花の雨」で有名になった絵がモデルらしい。




鶏・鳩や生活用品が売られているバザールを見学。
昼から莫高窟見学。莫高窟は敦煌の町から東南25kmの小オアシスにあった。東は三危山、西は鳴沙山で、石窟群は鳴沙山の東端の崖にあった。

BC366年、ある和尚がこの崖下に立つと、向かいの三危山が金色に輝き、何千もの仏の姿が、光の中に見えたような気がしたらしい。
和尚はここを聖地とし、崖に石窟を掘って住み修行をした。これが莫高窟の始まりだそうだ。
シルクロードを旅する人々は、ここに石窟を掘って旅の無事を祈って奉納したとのこと。4世紀から14世紀にかけてその数は千以上になり、千仏洞と呼ばれた。井上靖の「敦煌」では経典を隠した場所を千仏洞と言っている。

バスが着いたシルクロードの大画廊で世界文化遺産の莫高窟は整備が行き届いた観光地になっていた。もっと寂れた場所を想像していた私にとって何か場違いな感じをもった。
案内人の話では、今492の石窟が残り、2200余の塑像と4万5000㎡余の壁画があるらしい。
私たちは順番に特別窟3箇所、一般窟7箇所見学した。塑像や壁画は2000年前のものとは思われないほど色鮮やかだった。
17窟の右側の小さな穴倉がかの有名な経典類の保存庫だったとは、実際に目の前に立って感激した。
井上靖の小説「敦煌」の主人公「趙行徳」になったような錯覚を覚えた。
敦煌芸術は、東伝したガンダーラー仏教芸術と、中国固有の民族芸術が融合した新しい芸術らしい。
敦煌では、莫高窟の492の石窟の内、270に飛天があるそうな。飛天たちは天宮十宝山に住み、酒や肉を口にせず、花を集め、自由に空を舞うことが出来るとのこと。



唐中期の第158窟の、巨大な涅槃仏はあまりにも良い顔なので見入った。第275窟の交脚弥勒も珍しかった。
砂漠で隊商が盗賊に襲われる場面や、張騫が武帝に別れを告げる場面もあった。正しくここはシルクロードの美の殿堂だ。
しかし少々多すぎた。疲れて歩くのもいやになった。
正直言って見学が終わった時はほっとした。

日中は温度が高く暑いので涼しくなる夕方から鳴沙山見学だ。ビールと夕食を済ましバスに乗る。
敦煌から南へ5kmにある砂漠の奇観。小さな湖「月牙泉」。東西224m、南北の幅の広いところで39m、深さ約2mで三日月形。古来、砂丘の間で流砂にも埋没しない静かな湖。


ここから駱駝に乗って鳴沙山に行く。駱駝に乗るのは初めてだ。鳴沙山はさらさらした砂で出来ており、その風景は「月の砂漠」そのものだ。妻はこわごわ乗っているみたいだが、私は楽しくてしょうがなかった。
今回の旅で私が一番楽しみにしていたのは、駱駝に乗って砂漠を歩くことだった。本当は月夜に砂漠を旅したいがそうもいけない。
20分足らずの駱駝の歩行だったが、面白かった。
鳴沙山は東西40km、南北20kmの、砂だけで出来ている山。海抜は1650mだが、ここでの高さは50~60m。上から滑って降りると音が出るから鳴沙山というらしい。
山に登って橇で滑っておりることにした。日頃は3000m級の山に登っている私だが、お酒が利いて階段を登るのがえらかった。
橇は方向をとるのが難しく何回かこけそうになった。妻は下でみていた。






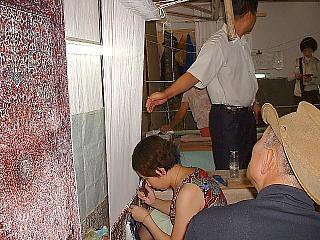

夜になって少しは涼しくなり、案内人の清さんに連れられて、バザール見学となった。夜の9時頃なのに昼間ほど店は出ていなかった。
親しくなった活発なAさん、実は彼女は今年から私の出身高校の社会科の先生らしい。夫婦ずれのJさんと一緒に屋台のシシカバブを敦煌ビールで食した。妻は足のマッサージをするといって先に帰った。
家族でシシカバブを焼いており、親父さんの被っている帽子から回族とみたが、聞かなかったので分らない。可愛い娘さんも手伝っていた。







ホテルに帰ったが妻はまだ帰っていなかったので、私も足のマッサージを覗いて見ることにした。
妻と年配の夫婦が若い女性にマッサージしてもらっていたので、私もついでにしてもらった。1回2000円だった。
歩き疲れていたのか非常に気持ちよかった。
7月31日(土)、今日は終日敦煌見学だ。
敦煌の西北約100kmにある「玉門関」。「春風わたらず玉門関」と謡われたここは、西の方ここを出ずれば故人無からんと言う意味だ。
まさしくここから西は辺境の地であり、不毛の砂漠で人は住んでいない。勿論知っている友も居ない。
いわゆる西域で今の新疆にあたるのか。
この有名な場所を訪れるのかと思い、胸が締め付けられるようだ。車はゴビ砂漠を走る。振動が激しい。妻は気分を悪くしたみたいだ。




昔は砂漠の真ん中を四輪駆動車で走っていたみたいだが、今は有料道路になっている。今の中国を反映して民間企業の道路だ。
道路の両側は50cmほどの溝と掘りあげた土が盛ってある。このゴビ(小石混じりの砂礫)は約50cm堆積しておりその下はさらさらした砂だ。道路に進入しょうとする車は砂にタイヤをとられて空回り。つまり只入りは許さないと言うことか。
途中に日本の「敦煌」を撮影したときの映画村があった。なんでも3億円かけて作ったそうな。バスの中から見ただけだ。
やっと砂漠の真ん中にある玉門関に着いた。
西域の和田(ホータン)でとれた美玉が、ここから中原に入ったので、玉門関というと伝えられている。
井上靖の「崑崙の玉」では、黄河の源流地帯の崑崙山脈となっているが、本当は光り輝く玉は何処で産したのか。
この遺跡は漢の万里の長城で、東西の長さ24m、南北の長さ26.4m、高さ9.7m。四角い版築の土塁で、南北に門が一つずつあった。
周りには柵がしてあり、入ることはできなかったが、私はぐるりを一周した。記念に小石を二つ拾った。
玉門関の周りには狼の糞を燃やしたと言う「烽火台」がいくつかあった。
玉門関の傍に管理人も兼ねている様子の土産物店があった。中は薄暗く埃だらけである。
冷やかしに入ってみると、雑多の模造品が彼方此方に無造作に置いてあった。
私は王様でもなく大金持ちでもないので、宝石類に縁がなく、まして玉を欲しいと思ったことは無いが、店内を歩いていると碁石があった。
石をくり貫いた器に入ったメノウの白石・黒石だ。私は関西棋院から三段の免状を頂いているかっての碁キチだ。最近はあまり打っていないが、やはりこの碁石は欲しかった。メノウも玉の一種ではないか。玉門関で玉を手に入れるとは恰好いいじゃないか。
値段はかなり高そうだ。「多少銭」(ドウオ シャオ チェン 、幾らですか)と聞くと、かなり高い金額を言った。日本円で何万円だ。
様子では骨董品だからと言っているみたいだ。
同行のAさんは中国語を嗜み、簡単な会話を教えて貰っていたので、高い高い(エグイヤー、エグイヤー)と言って買わなかった。
本当は欲しかったが私の財布には、数万円ものお金は入っていなかった。


玉門関の近くに漢代の長城もあった。この長城は昔見た万里の長城のように立派でなく、低い風化した長城だった。何でも匈奴の馬が飛び越えない高さがあればよかったらしい。
敦煌への帰り道で「蜃気楼」を見た。気温が上がって来た為らしい。薄ぼんやりとではあるがきらきら光る水のようだ。
山で見るブロッケン現象と又違う地平線に浮かぶ現象だ。砂漠を横断する旅人は、喉の渇きから水場に着いたと喜ばされたことだろう。


午後からの見学には、妻は車酔いでパスをするという。
経典を運んできたと言う白馬が死んだところに建てられた「白馬塔」を見学。昼過ぎの為、猛烈な太陽に照らされて、じりじり焦がされていくような感じだった。
敦煌博物館は、珍しいものもあったが、案内の職員が最後に玉や骨董品のセールスを始めたので、私は抜け出して下の売店を覗くことにした。
店の一隅に玉門関で見た同じ碁石があった。私は高根の花と諦めたが、念のため博物館の職員に値段を聞いた。
やはり日本語で6万円と言った。私はやはり「エグイヤー、エグイヤー」と言ったところ、彼女は私が中国語を話したので脈があると感じたのか、「貴方は幾らなら買うのか?」と興味を示した。私がどうせ買えないのならと「私はお金が無い。8千円なら買ってもよい」と言えば、彼女は3万円なら売っても良いというではないか。
それから何回かの交渉があり、結局1万円で私は「黒白の玉」を手に入れた。
勿論交渉は「エグイヤー、エグイヤー」の連発と、身振り手振りだった。
私はこれまで幾つかの外国を旅しているが、身振り手振りの万国共通語で意味の通じなかったことは殆ど無い。
私はこの碁石が本当にメノウのものであるとの「証明書」をくれと言ったところ、「瑪瑙団棋」700元と書いた敦煌市の捺印がある、日本で言う領収書をくれた。そして敦煌市の捺印を示して「国が保障しているから間違いない」という態度を示した。
まあー国が保障しているなら、これは間違いなく瑪瑙という玉だと納得し、以後私の宝物として大事にしょうと思った。
後でA女史にお礼を言ったことは言うまでもない。
石の器と黒白のメノウの玉で重さは約10kgあり、帰りのスーツケースは仲間で一番重い30kg(普通は20kg以内)となった。
早めの夕食は和食だった。バスで2時間かかって鉄道の駅に着いた。列車に泊まってここ敦煌から「火州」と言われるトルファンに行く。





ここは柳園という土地だが、最近の観光ブームで駅の名を「敦煌」にしたらしい。
今回の旅で強く感じたことは、最近の中国は民間主導の資本主義経済をかなり取り入れているみたいだ。儲けて利益が出るなら、歴史的な価値や環境を守ると言うことは二の次になっているみたいだ。10年前の中国には、ここが社会主義の国なのだという感じがあったが、今回の旅では商業主義が蔓延している日本と変わらない印象を受けた。
待ち時間に駅前をぶらつき、ビールやソーセージのツマミ類を安く手に入れた。
夜行寝台車は4人で一つのコンパートメントだった。私達夫婦との同室者は私より少し年配のKさん夫妻だった。
外側の夕陽が美しく、暗くなるに従ってビールや焼酎の宴会が始まった。
Kさんは大阪の有名な高校・大学を卒業して教師をしていたみたいだ。今は共働きをして勤めている妻を助けて「主夫業」だと笑っていた。


奥さんも先生でなんでも同行のAさんと同じ職場の時もあったみたいだ。世間は狭いとつくづく感じた。
Kさん夫婦と私達夫婦は境遇も良く似ており、かなり突っ込んだ話も出て、楽しい夜行列車の旅だった。
約8時間の旅だったが、数時間は2階の寝台でぐっすりと寝た。
(2004.8.27)
続く
「中国シルクロード旅行」ページに戻る