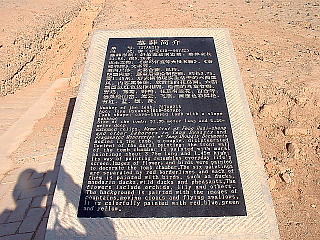トルファン(2004.7.28~8.4)
8月1日(日)、トルファンにはまだ薄暗い早朝に着いた。まず本日の宿「トルファン大飯店」に行き、中華料理の朝食となった。ここの朝食はたいして食欲をそそるものが無く、持参の「きつねうどん」にお湯を掛けてもらって食べた。皆から羨ましがられた。
Aさんも同じ思いだったらしく、近所で買ってきたまんじゅを貰った。美味しかった。
トルファンは、漢代に車師国があったところ。その後、六つの西域小政権が、つぎつぎにここに高昌国を建てた。唐代には西州と称し、元、明の時代には火州と称した。漢代以来、シルクロードの要としてトルファンの歴史は長い。ここは世界で第2、中国で第1の海抜の低い所だ。盆地の半分が海抜ゼロメートル地帯で、最低点のアイディン湖はー154mにある。
又、火州という名の通り、中国で最も暑く、40度以上の高温が年間40日余りある。年間降水量が16mm以下で、蒸発量が3000mmという乾燥のため、この独特の気候が、大量の文物を保存したともいえる。









今日は終日オアシスの街トルファン観光だ。
まず最初は6世紀より14世紀にかけて建造されたベゼリク千仏洞だ。ベゼリク千仏洞はトルファンの東40kmの火炎山中央部にある。
現存83箇所洞窟中の40箇所には壁画があり、壁画の面積は約1200平方メートルらしい。
洞窟内は写真禁止の為、自分の目にしっかりと焼き付けた。壁画内容は仏教の大乗経典の因縁物語と千仏などであった。色鮮やかな彩色が今日まで良く残されたと感心した。しかし残念なことはここの壁画が世界各国の考古探検隊によって無残にも切り取られて持ちさらわれたことだ。その中に日本の探検隊も加わっていたことは悲しいことだ。
先進国が後進国の宝物を考古上の学問の為という理由で持ち去るのはおかしい。これらはスペイン人がペルーのインカから金銀財宝を盗んだこととさほど違わない野蛮な犯罪と言わざるを得ない。こうした略奪した宝物・文物は返還すべきと思うが、そうすれば大英博物館等は魅力の無いものになってしまうだろう。
トルファンの現地案内人はウイグル族のグルさんという女性だ。典型的なウイグルの顔立ちだ。彼女に井上靖の「敦煌」の女性を見出した。記念に彼女を挟んで写真を撮ってもらった。
シルクロードで世界に聞こえている新疆は、昔から多くの民族が集まり住む地方である。現在の総人口は1600余万。民族が47を数え、そのうちウイグル族が主体で約半数を占める。ついで漢族、カザフ族、回族、蒙古族、キルギス族、シボ族、タジク族、ウズベク族、満州族、タオール族、タタール族、ロシア族等である。




次に孫悟空が活躍した火炎山。ウイグル語で「赤い山」という。火炎山は長さ約100km、幅9km、最高851mの山脈。印度へ経典を取りに行く玄奨法師も通った所。
むき出しの赤い山は燃えるようだった。山の色が赤いから、盛夏の気温が80℃以上になり、岩石が熱くなり、気流が流れ、立ち昇る激しい炎のようである。「西遊記」では、孫悟空が芭蕉扇を借りてきてやっと炎を鎮めたことになっている。
火炎山の碑の前で、ウイグル族の娘と一緒に写真をとって貰ったAさんは、撮影料金10元の他に、帽子代として更に5元も取られたと言ってぼやいていた。














火炎山のすぐ南にある高昌故城。5世紀に匈奴の後裔が高昌国を建て、9世紀にウイグル人がまた国を建てたが、13世紀の戦乱で高昌城は破壊された。高昌城の区画は唐の長安と良く似ているらしい。城の面積は200万㎡。城壁は周囲5kmで三重になっている。
城の見学は中心地までロバの馬車に乗って行くことになった。なにせとてつもない熱さだ。歩いていけば体が焼けてしまうような猛暑だ。
ロバ車の御者は日本語で「ロバがんばれ」といって皆を笑わせていたが、手綱をそっちのけに鈴売りの商売を始めたのにはまいった。
私の妻が勧誘に返事をしたものだから、「貴女と私は友達、友達」と言って商売しだした。
あまりのしつこさに我々はしらけてしまった。
一番奥の寺院跡に着いた。ここで玄奨法師は講話もしたらしい。法師は高昌国王の手厚いもてなしを受けた。国王は印度へ行かずに留まって欲しいと頼んだが、玄奨法師は志を変えず、感動した王は金銀や馬を餞に贈ったという。
城内の建築は、日干し煉瓦を積んだ建物であるが、彼方此方に崩れ残っていて、ドームがあったり、階段式の仏塔があったりして千年以上前の雰囲気が感じられた。

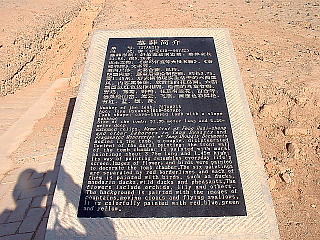


高昌故城の北にあるアスターナー古墳群。現在までに発掘調査の終わった400余りの古墳から大量に出土した文物は、ウルムチとトルファンの博物館に納められたという。墓道の階段を下りていくと、ひんやりとした花鳥の壁画がある場所にミイラが眠って居た。何百ものミイラがあったらしいが、私たちはその内の数体を見た。千年以上前の人間と思われないような保存状態だ。着ていた絹等の色も感触も当時のままだ。夫婦の手を繋いだミイラもあった。ここは乾燥地帯である上に、地下水位が低いので保存状態が良いのだろう。
午前中の余りの暑さに妻がダウン。午後の観光は中止してホテルで留守番。夕食のイスラム風味料理と、ウイグル族の歌と踊りは見に行くとのこと。





昼一番に1777年建造のモスクで、塔は37m、表面の幾何模様が美しいウイグル建築の「蘚公塔」見学。新疆に現存するイスラムの古建築中最大の塔らしい。バスから降りてこの塔の入り口まで歩いた時の暑さは、私の60年の一生の内最も熱かったと思う。焼き殺されるかと思うほどの熱さだった。うだるような暑さを超えていた。
塔の中はひんやりとして気持ちよかった。中から眺めた周りの風景は、緑豊かなオアシスだった。









交河故城は、トルファンの西約10kmの所にあり、紀元前2世紀に建てられ、期限14世紀に廃墟となった。今の故城は、ヤルナイゼ川の中州で、長さ1650m、最大幅300mの木の葉形の台地である。周囲が2つの川に挟まれ、高さ30mの断崖に築かれた天然の要塞である。
前漢の時代、車師前国の国都として栄えた都市である。
ここにはロバ車がなく、幅3m長さ350mの都大路を黙々と歩く。熱かった。周りは日干し煉瓦の古代の建物跡。木陰一つも無い。
寺院跡は敷地5000㎡、井戸の跡もあった。城内には101の仏塔があったらしい。城門や役所らしきものもあった。民家は土で壁を築き、炎熱を避けるため地下式もしくは半地下式の構造だった。
ここの入り口の売店で音楽好きの息子の土産にホルンのような古い楽器を買った。骨董品らしきもので最初は2万円と言っていたが、最後は350元で買った。ここでも品質保証書を要求したら、碁石と同じように領収書に印鑑を押してくれた。
トルファン盆地の北側は、草一本ないぎらぎらした岩肌が火を吹きそうな火炎山だ。ところがこの山の麓は谷川が小オアシスを作り、カレーズが農地を潤して、水は豊かなのだ。天山の雪解け水をゴビに浸み込んだ地下水を、暗渠を掘って地上に導き、明渠にして灌漑している。2000年以上の歴史があるらしい。暗渠は3kmから30kmでトルファンとハミに集中しているらしい。
土掘りと通風の為の井戸のような竪坑が20mから30mごとにある。



トルファンのカレーズは1158本、総延長3000km以上で、その規模の雄大さに恐れ入った。
カレーズの中は涼しく、5角(約7円)で飲んだ一杯の水は、味はしなかったが爽やかで美味しかった。かって中央アジアのブハラで食べたウリに当たって腹をこわした私だが、今回はなんとも無かった。ゴビの砂漠を潜り抜けてきたカレーズの水は、正しく立派な飲料水であることを身をもって証明したことになるだろう。




西域で葡萄といえばトルファンの葡萄溝が有名だ。火炎山の西にある幅500m程の峡谷が、風光秀麗、用水路が縦横に走り、音を立てて流れる水がオアシスを作っている。
ここに谷を埋めて延々南北8km、東西500mの葡萄の世界「葡萄溝」がある。特産の種無し白葡萄、赤葡萄、色、形、味、大小とりどり200種類もの葡萄があった。葡萄は前漢時代の張騫が西域に使いした時、大宛(今のフェルガナ盆地)から持ち帰ったとされる。
玄奨法師が高昌国を通過したとき、ここの谷の水を飲んで一休みした時、途中で手に入った葡萄を出して食べた。その時の種が根を下ろして、今のような葡萄の王国になったと言う伝説もあるらしい。
ここでサービスで食べた小さな種無し葡萄は本当に美味しかった。
ここの売店は種々取り取りの干し葡萄が主であったが、民芸品も売っていた。
古いナイフは無いかというと、奥からさほど古くは感じられないナイフを持ってきた。記念に100元で買うと、更に奥から今度は羊の皮で縁取りした骨董品らしいナイフを出してきて、500元でどうかと言う。私はさっき買ったばかりだから「要らない」というと300元ではどうかとしつこく言う。私は欲しかったが120元と言ったら、「とてもそのような安さでは売れない」と立ち去った。
集合時間も気になり、入り口に向かって帰っていると、先程のウイグル人が追いかけてきて、「仕方ない。150元で」言うではないか。私はOKと言いかけたが、念のため今までの言いがかり上「120元なら」と言ったら怒って行ってしまった。
今でもあのナイフは欲しかったと思うが、値引き交渉は本当に難しく、折り合いのつけるタイミングも大切と反省している。
30元の差とは数百円でやはりあのナイフは手に入れるべきだったと悔しがる私である。
バスでホテルに戻り、妻たち留守番組みを乗せて、イスラム風味料理を食べた。
その後ウイグル族の歌と踊りの夕べ鑑賞となった。
それなりの楽しい踊りであったが、踊り子たちの魅力はもう一つであった。
私はウズベキスタンで見た、サマルカンドのミレットに囲まれた広場での、タジク人の踊り子のペリーダンスのセクシーでありながら淫らさが無かった踊りと比較していた。


タジク人はイラン系の色白で、混血らしく目鼻立ちの整った内面的な美しさを持った少女だった。
月の砂漠を駱駝に乗って旅するお姫様はきっと彼女のような人だと想像していた。
(2004.9.16)
続く
「中国シルクロード旅行」ページに戻る