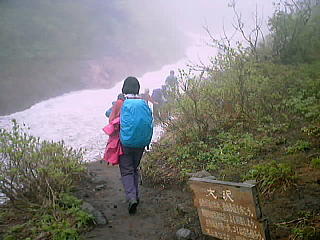地の果て「羅臼岳登山」
深田百名山の内九つの山が北海道にある。しかし私は一つも登っていない。
今回「サンケイ旅行会」が羅臼・斜里・雌阿寒岳と道東知床半島付近の三山の登山を募集した。
先週「焼岳」を登り、来週ロシア旅行を控え日程的に少々苦しいが、チャンスは多いに利用する精神で申し込んだ。
7月5日(金)、妻に生駒駅まで送ってもらって、関西国際空港を8時50分発、帯広空港に10時45分着。
今回は大型台風6号が日本に接近してきている為、全国的な雨模様。殆ど雨を覚悟していた。場合によっては登山を諦めざるを得ない。

ここは北海道。ひんやりする。リーダーの荒木さんと角崎さんを除いて、総勢14名。男5名、女性9名。Tさん夫婦と女性5名はグループだ。
男性は71歳の京都のOさん、神戸の私と同年のOさん、63歳のTさん。単独の女性は3名。
帯広空港から本日の宿泊地ウトロまで、バスで半日行程だ。ゆったりと座り、北海道の大自然を車窓から眺め堪能する。じゃがいも畑、ピートという砂糖ダイコン。草を食む馬や牛達。広い広い牧場。冬の為のくるくる巻かれた飼料。
私の「かわせみ農園」とはえらい違いだ。
じゃーここで牧場を買って永住するか。都会から完全に離れ、半年以上雪に閉ざされる生活に果たして耐えられるか。家畜を飼うということは、毎日世話をするということ。大好きな海外旅行もお預けだ。そうそう山登りも出来まい。やっぱり自信がない。
やはり私は今の自分の環境にあった「かわせみ農園」を中心に考えることにしょう。
バスは十勝川温泉を過ぎ、池田の葡萄畑を見つつ、今注目のアショロ(足寄)の町に入った。ムネオと松山千春の生まれた町で有名だ。
昼食のイクラ丼を食べ、オホーツク海の海べりで野に咲く「ハマナス」を見、夕方右前方に明後日登る「斜里岳」のなだらかに広がる裾野を見つけた。斜里岳は印象に残る美しい山だった。
ウトロの
「知床第一ホテル」に到着。
知床は30年前に妻と一歳半の娘と3人で訪れたことがある。その娘が今年の3月に可愛い孫娘を生んだ。早いものだ。
ホテルの部屋と温泉は良かったが、夕食と朝食がバイキングだったことにはげんなりした。バイキングは忙しない。
6日(土)朝7時ホテル出発。岩尾別温泉の「ホテル地の果て」にバスが止まる。知床はアイヌ語のシルエトク(大地の果て)に由来するという。確か30年前にはこの「地の果て」ホテルに泊ったのではなかったか。記憶が定かではない。
ここの標高は260m。羅臼岳の標高は1660m。標高差1400mをこれから往復することになる。「焼岳」では1000mだった。なんとか足が吊ることも無く登ったが、そろそろ限界だったことは私が一番知っている。
木下小屋前から広葉樹林の中を大きな電光形で尾根に取り付く。7時50分。天気は予想に反して曇り。ゆっくりと歩く。尾根の上に出ても樹林に覆われて展望がきかない。やっとオホーツク展望台の岩峰に着く。8時45分。標高580m。320mを1時間足らずで登ったことになる。私のペースだ。ちっとも疲れていない。
さらに林間の尾根道を辿り「弥三吉水」に着く。ここは水場だ。冷たくて美味しかった。9時24分。標高825m。
71歳のOさんが遅れだす。百名山をこれまで70数箇所登ったと言っていたが、やはり年には勝てないのだろうか。
百名山を登るには三つの困難な山があるという。高さとか取り付きとか交通事情もあるだろう。一番は北海道日高山脈の最高峰「幌尻岳」だ。二番目は新潟・山形・福島三県にまたがる「飯豊山」。三番目は北海道第二の高峰「トムラウシ」。
やはり山登りは気力と体力が無ければ登れない。Oさんのように気力は十分だが、体力が付いていかない場合も多くなるだろう。
私は今年中に「飯豊山」と「トムラウシ」に挑戦するつもりだ。
少しの登りで傾斜のゆるい極楽平となった。足の弱い(吊りやすい)私にとっては極楽だ。そこを過ぎたら急斜面だった。
途中淡黄色の花のウコンウツギがあっちこっちにあった。エゾノツガザクラのピンクの小さな花も見た。
10時22分、標高1090m。最終水場の銀冷水に着いたが、川の水は飲めるような感じでは無かった。Oさんは引き返したそうな。本人は大変残念だったことだろう。
やがてコースは左手の沢筋に出、雪渓を登ることになる。ひんやりとした空気が気持ちよい。足元を確かめながらアイゼンを使うことも無く登る。行けども歩けども雪渓だ。誰かが「あ、リスだ」と叫ぶ。岩陰に隠れるリスの尻尾を見た。リーダーは「あれはオコジョだ、この高さにはリスは居ない」という。ここの雪渓は私の記憶では白馬の大雪渓に匹敵する。
登りきった所が待望の「羅臼平」だった。11時20分。標高1395m。ここはハイマツの原であり、見事なお花畑だった。いろいろな花の名前を女性陣から教わったが殆ど忘れてしまった。
ここにリュックを置いて、空身で登る。
12時17分、やっと羅臼岳頂上(1660m)だ。天気は晴れているが展望がきかない。硫黄岳は確認出来たが、すぐ近くの国後島が霞んで見えなかった。深田久弥は霧の為何も見えなかったらしい。「ただすさまじい風の音を聞くだけだった」と言っている。それに比べて我々はついていたと言えるだろう。1400mの高度差を4時間ちょっとで登ったことになる。足は全然どうもない。自信がつく。これなら百名山完登も夢じゃない。
羅臼はアイヌ語で「鹿、熊などを捕ると必ずここに葬った為、その臓腑や骨のあった場所」という意味だそうだ。ラは「動物の内臓物」、ウシは「たくさんある所」というそうな。ラウシと呼ぶのが正しく、古い地図にはラウシ(良牛)と書かれていると深田は言っている。
午後1時36分、羅臼平で昼食のおにぎりを食べる。
帰りは同じ道を降る。銀冷水で雪渓の下のパイプを探し、水を飲む。北海道の水はキタキツネの関係で怖いと言う話だが、潜伏期間が10数年と聞き、まあいいかと勝手に決めて飲んでしまった。美味しかった。
4時49分に木下小屋に帰ってくる。3時間足らずで1400mを降ったことになる。体も足も疲れていない。先週の「焼岳登山」が良いトレーニングになったのだろう。
バスでの帰り道に「オシンコシンの滝」を見て、斜里の「駅前ホテル斜里館」に着く。風呂に入って宴会だ。皆と親しくなる。
三山の内、最難関の「羅臼岳」を登頂したことで気分的に楽になった。深田百名山の49座目だ。大満足。
(2002.7.9)終わり
羅臼岳(2002.7.10)
羅臼岳(2002.7.10)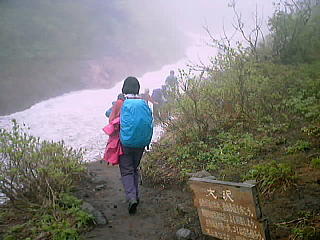
羅臼岳(2002.7.10)
羅臼岳(2002.7.10)
羅臼岳(2002.7.10)
羅臼岳(2002.7.10)
羅臼岳(2002.7.10)
「深田100名山登山記録」ページに戻る